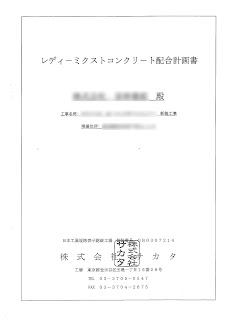配筋検査で指摘した是正項目を確認し、さていよいよコンクリート打設です。
現場が最も緊張する一日。やり直しが原則効きませんので慎重に実行します。
数日前にコンクリートの配合計画をコンクリートプラントから提出してもらい、設計図に記載通りの配合で計画しているかをチェックしておきます。
先日の配筋検査やコンクリートの打設については日本建築学会のJASS5、国交省の公共工事監理指針を基準に監理していきます。
現場では受け入れのためにコンクリート配合計画の通りであるかの確認をします。
現場では空気量、塩分、スランプ等のコンクリートの性能に問題が無いかを確認します。
ここで問題があれば打設中止などを指示しますが、無事OK。
コンクリートは4週間程で狙った強度が発現します。
写真左にある丸い筒のようなものにコンクリートを同時に詰め、コンクリート打設後、1週目、4週目に強度圧縮試験を行い狙った発現強度が出ているかを確かめます。これをテストピースといいます。
もし強度が出ていなければ取り壊して再工事・・・なんてならないように設計上ではコンクリートの強度は余裕をもって設定しています。
型枠内は綺麗に清掃して、最下部からゴミなどが取り除ける用に穴をあけています。その穴を塞ぎいよいよコンクリート打設。コンクリートミキサー車5台分を間隔無く打設していきます。
コンクリートは水、セメント、砂、骨材(小石)を練り合わせたものです。コンクリートが途中で分離しないように打設口までの角度を注意して打設。
おこのみ焼きの生地を作るときにも様々なものを入れますが、分離しては美味しくない!そういうことです。ちょっと違うか。。
写真右のおじさんが突っ込んでいるものはバイブレータという振動する機械です。振動でコンクリートを液状化させてコンクリート密度を高めて不要な混入空気を除去、骨材(小石)が均等に分布するようにします。結果、きれいなコンクリートが仕上がるのです。
地下部分はコンクリート打ち放し仕上げ。通常のコンクリートよりさらに綺麗に仕上げなければいけません。
ここで登場するのが・・・
節付きの竹なんです。この竹でツツイていきます。超アナログですがこれが一番の方法であるとは建築業界では周知の事実。現場監督自らツツイていきます。現場監督さんについている若い監督さんも一緒に全周ツツイていきます。
簡単に見える竹ツツキ。下手な人がやると逆に型枠を傷つけて傷がついたりしますので、監督が若い監督に指導しながら竹をツツイていきます。
コンクリートは打設後に十分な期間をもって型枠を外します。工期的に十分な時間が取れない時は、先にコンクリート圧縮試験を行い十分な強度が出ているかを確認して脱型します。
このたびは4週間バッチリとっての脱型となっています。
このコンクリートあなどるなかれ。
一様に同じに見えるコンクリート。実は使う場所によって様々なコンクリートがあります。
超高層等自重が重い建物は当然高強度のコンクリートが使われますし、工期等の理由から早く強度を出したいときは早強コンクリート等、配合により様々に使い分けます。
すでに終わってしまいましたが強度を競うコンクリート甲子園なるものまであるのです!
http://www.jsca.or.jp/vol2/15tec_terms/200506/20050625-2.html
そういや知り合いの現場監督がドーハに転勤になったときに「あんな暑い国速攻でコンクリート固まるのにどうやって打つんだよ。」と言っていました。どうやら朝方、夕方が勝負らしいのですがそれぞれの地域で独自のノウハウがあるんだろうな。